どうも、太陽は灼熱した石、と言って、神に対する侮辱行為として危うく処刑されかけたアナクサゴラス、ではなく西郷十です。
今回の記事はアメリカの授業で、課題として使われる教材をテーマに記事を書きましたので、ぜひ最後まで読んでいってください。
どのような本を読むのか
アメリカの学校は1st semester(1st 9 weeks, 2nd 9 weeks)と2nd semester(3rd 9 weeks, 4th 9weeks)の二つの学期に分かれていることは、他の記事からみても、見て取れます。
そして、アメリカの高校の英語の授業において、一つのsemester につき、二冊ほどの本を、授業課題として読みます(期間としては、三、四週間ほど。)
初めに、この場では、どのような本を読むのかを、ざっくばらんに説明していきます。
1、長編小説
2、短編小説
3、ドキュメンタリー小説
4、戯曲(劇)
前記したものが主に読む本のタイプです。
どれも、読んだことはないけど一度は聞いたことがあるようなものばかりです。
例えば、長編小説だと「グレイト•ギャツビー」や「エデンの東」、戯曲ですとシェイクスピアだったり、英語文学において歴史が深く、さらに著名なものばかりです。
そのためか、文は非常に難しく、一長一短ではなかなか読めません。
そして、学習の最後にはテストがあるため、ただ読むだけではいけません。
下記に、読み方や勉強方法などを伝えていけたらと思います。
読み方のすすめ
読み方といってもいろいろあります。
特に工夫もなく、読んでいる過程で見覚えのない単語やフレーズを調べていくだけでも、時間はかかりますが読めないということはありません。
ただ、そんな時間がかかる方法ではなく、もっと早く読み終わりたいという方は、初めに翻訳版を読むことをおすすめします。
上記にもある通り、課題として選ばれる本は基本的に有名どころが多いです、そして必然的に翻訳版がすでにあることもよくあります。
筆者の実体験になりますが、学校で「キャッチャー•イン•ザ•ライ」を読んだ際は、初めに翻訳版を読んでから、原文の方を読んだ結果、想像以上にすらすらと読めました。
他にも、YouTubeなどで、本のさわりの部分を解説している動画などをちらほら見受けられるので、そちらの方もお勧めしておきます。
英語の授業のテストの勉強方法
私が最もおすすめする勉強方法は、登場人物と話の流れを繋げながら覚える方法です。
やり方といっても、特に難しくはありません。メモを片手に本を読みながら、自分が重要だな、と思ったことを、逐一箇条書きでもいいので書き記していくと、読み終わった後も、メモを使えば最初から本を読む必要がなくなります。
まとめ
今回の記事はやや西郷十一の趣味で書いてしまったのですが、いかがだったでしょうか。
もっと知りたいかたはお手数ですがQ&Aコーナーから教えていただけると嬉しいです!!
それではまた、別の記事で。

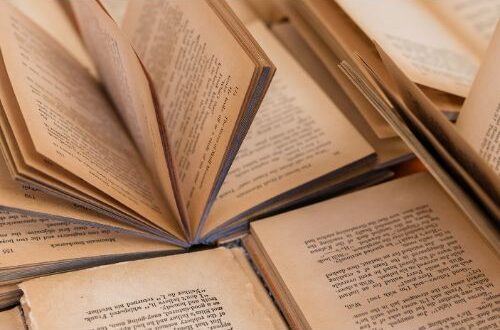


コメント